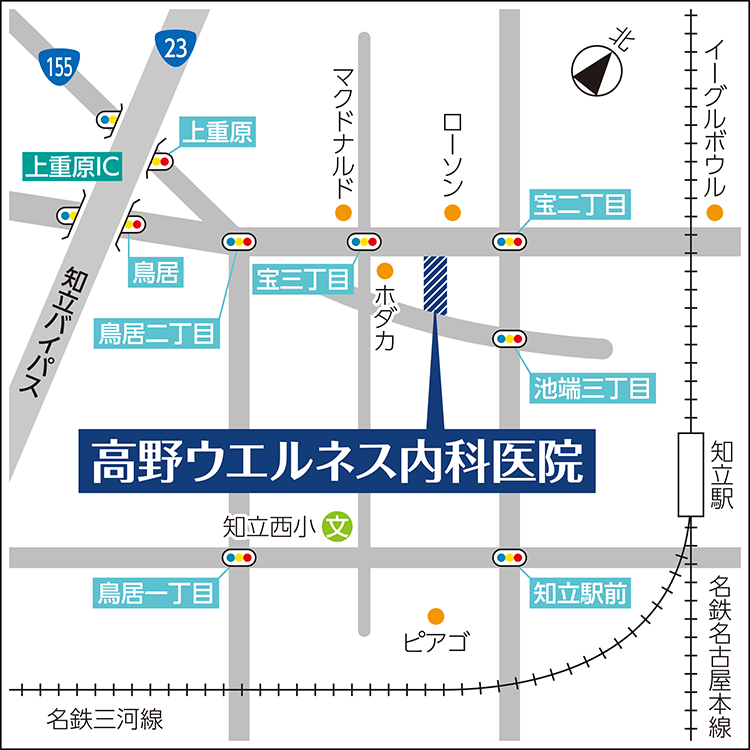アレルギー科について

アレルギー疾患とは人体に悪影響を及ぼす細菌やウイルスなどの外敵を攻撃し排除するための「免疫機能が暴走」し、本来は人体にそれほど有害とは言えない「食べ物」「花粉」「ほこり」などに対して「過剰反応」してしまう疾患群を指します。
結果として、本来は「自分自身を守る」はずの「免疫反応」が「自分自身を傷つける」「アレルギー反応」となってしまうのです。
多くのアレルギー疾患は小児期に頻度が高く症状も強いものの、成長とともに徐々に改善していく傾向がみられます。
なお「免疫反応」が「自分自身の組織」に反応し攻撃してしまう疾患群を「自己免疫疾患」といい、リウマチ、SLE、腎炎、自己免疫性肝炎、自己免疫性膵炎、シェーグレン症候群など多くの疾患が存在します。
当院では「アレルギー性鼻炎」「気管支ぜんそく」「アレルギー性皮膚疾患」などアレルギーに関連した疾患の診療をお子様から大人の方まで行っております。
自己免疫疾患についても診療いたしております。
また「アレルギー性紫斑病」「紫斑病性腎炎」などもアレルギー関連疾患で、皮膚科や内科との間に存在する疾患と言えます。
これらの疾患についても診療を行っております。
アレルギー疾患はメタボリックシンドローム、ストレス、メンタル、自律神経、ビタミンやミネラル、腸内環境、などと密接な関係があるため、トータルな治療が肝要です。
主な疾患
気管支ぜんそく
咳、痰、呼吸苦を症状とし、呼吸時に「ヒューヒュー」「ゼーゼー」と特徴的な音が聞かれます。
咳を主症状とする「咳喘息」という病態もあります。
「アレルギー性炎症」により「気管支が炎症」し空気の通り道が狭くなり、強い発作の場合には生命にかかわることもあります。
アジアの歌姫といわれたテレサ・テンさんは喘息発作で亡くなられました。
喘息治療で重要なことは「発作を起こさせない」ということです。
現在は「優れた抗アレルギー剤」が出そろい、さらに「操作も簡単な優れた吸入薬」も登場しています。
抗アレルギー薬を上手く組み合わせて内側からのコントロールを基本にしますが、これに優れた吸入薬を組み合わせることでほとんどのケースで良好なコントロールが得られます。
アレルギー性鼻炎
周知のとおり国民病ともいえる疾患です。
スギ花粉などが原因で「アレルギー反応」を生じ「鼻粘膜」や「眼球結膜」に「アレルギー性炎症」を生じ鼻や目の辛い症状となってあらわれる疾患です。
気管支ぜんそく同様「発作を起こさせない」ことが大切です。
「抗アレルギー薬」の内服を軸に「点眼薬」「点鼻薬」等を組み合わせていくことで良好なコントロールが得られます。
良好なコントロールを継続していくうちに脱感作が成立することもあります。
その他、スギ花粉とダニに対してのみですが「舌下減感作療法」もあります。
自律神経、ストレス、メンタル、腸内環境、ビタミンやミネラルの栄養状態、メタボリックシンドロームとの関連性も強いです。
アレルギー性皮膚疾患
アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、慢性蕁麻疹、薬疹、アレルギー性接触性皮膚炎=かぶれ、などを治療していきます。
「外用薬」のみならず「抗アレルギー薬」を適切に組み合わせて「内側から抑えていくこと」が大切です。
やはり「メタボリックシンドローム」との関連性があり「内臓脂肪過多・異所性脂肪過多」を改善していくことも大切であると考えております。
栄養、腸内細菌との関連も強いです。
食物アレルギー
食物により「喘息様の呼吸器症状」「下痢・嘔吐・腹痛などの消化器症状」「蕁麻疹様の皮膚症状」などが生じ、場合によっては緊急治療が必要となります。
「そば」「エビ」「カニ」「落花生」「小麦」「鶏卵」「乳製品」などは比較的頻度の高い食材と言えます。
原因と思われる食物の除去のみならず、抗アレルギー剤を適切に組み合わせ、症状をコントロールしつつ、脱感作=アレルギーからの解放、を目指します。
交差反応性により、アレルギー検査では特異的な反応が見当たらないにも関わらず、ある食べ物に対してアレルギー症状を呈するケースも多くみられるからです。
食物アレルギーに限らず、アレルギー反応の多くは交差反応性を有しており、全く無関係と思われる思わぬ物質がアレルギーの原因となっているケースが頻繁に存在します。
このような現象は、全てのアレルギー疾患に見られ、治療上の盲点になっています。
つまり、アレルギー物質の除去に躍起になることはナンセンスであり、アレルギー体質の改善=脱感作=アレルギーからの解放、を目指すことが重要であることを示していると言えるでしょう。
抗アレルギー薬をうまく組み合わせ、内側からアレルギー反応をコントロールし、徐々にアレルギーからの解放を目指していく事こそが本質的治療であると言えるのです。
そして、アレルギー物質の除去や外用薬での治療は本質的な対処とは言いがたく補助的な対処であると言わざるをえないのです。
刺虫症
「蚊」など多くの虫に刺された場合、痒みや痛みが生じますが、この反応が過剰となった場合もアレルギー反応を生じ、特に「ハチ」の場合は「アナフィラキシーショック」を起こし生命を脅かされることがあります。
「アナフィラキシーショック」は「ハチに2度目以降刺された」場合に多く生じます。
「スズメバチ」の場合は症状が重篤となり生命に危険が及ぶことがあるので1度目に刺された後は「エピペン」を所持し2度目以降に刺された場合に備えている必要があります。
当院医師は「エピペン処方登録医」ですから「エピペン」の処方が可能です。
気軽に「エピペン」についてのご相談をしてください。
「蚊」など一般的な虫に刺された場合でも、症状が激しい場合、あるいは長く続く場合にはご相談下さい。
アレルギー疾患がなかなか改善せずにお困りの方はご相談ください。
多面的にアプローチして必ずより良い結果を出します。